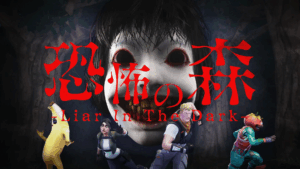「恐怖」だけでは満足できない、もっと強烈で過激な作品を探している人は少なくない。特に、流血や切断、拷問、人体実験などのグロテスクな描写を含むホラー映画は、いわゆる“耐性”のある観客から高い支持を集めている。今回は、視覚的・精神的インパクトが強烈な9作品をピックアップ。いずれも倫理の限界を問いかける内容であるため、視聴には十分な注意が必要だ。
『グリーン・インフェルノ』(2013年/アメリカ)
現代に蘇った“食人族”──助けに行ったはずが、食べられる側になる。
イーライ・ロス監督による本作は、カニバリズムをテーマにしたジャングルホラーであり、1970年代の伝説的作品『食人族』に対するオマージュともいえる。環境保護団体の若者たちが原住民に捕らえられ、生きたまま解体されていく描写は凄惨を極める。リアルな特殊メイクを駆使したシーンの数々は、観る者に強烈な嫌悪感と戦慄を与える。単なるグロではなく、「偽善的な善意」を問うメッセージも込められている。
『ムカデ人間2』(2011年/オランダ)
ただの映画に終わらない、現実に憑依する狂気の続編。
前作『ムカデ人間』に“影響を受けた”男が、さらに過激な実験を試みるというメタ構造が特徴の続編。モノクロ映像で描かれるが、その内容は前作をはるかに上回る残酷さに満ちている。排泄物、出産、性的暴力など、観るに堪えない描写が連続し、倫理性を意図的に破壊した作風となっている。多くの国で自主規制の対象となったことからも、その過激さは際立っている。
『サロ あるいは120日間のソドム(邦題:『ソドムの市』)』(1975年/イタリア)
芸術か、地獄か──映画史に残る最も過激な禁断の映像。
ピエル・パオロ・パゾリーニ監督による遺作であり、世界中で論争を呼び続けている問題作。舞台はファシズム末期のイタリア。権力者たちが若者を拉致し、拷問や性的暴力を加えるというストーリーが展開される。食糞や性的奴隷化といった極端な描写は、政治的支配と人間の尊厳をめぐる批評性を帯びている。芸術か冒涜か、評価が二分され続ける作品。
『オーディション』(1999年/日本)
“恋愛映画”の皮を被った、針とノコギリの地獄絵図。
三池崇史監督による異色作で、前半は恋愛ドラマ風に始まりながら、後半で一気に拷問ホラーへと転じる構成が特徴だ。電動ノコギリによる切断や、針を使った残酷な拷問シーンは、観る者の神経を逆撫でにするような痛々しさを伴う。国内よりも海外で高く評価され、特に欧米のホラー映画界では“カルト的存在”として知られている。じわじわと狂気が露呈していく演出は、日本ならではの恐怖表現と言えるだろう。
『哭悲 THE SADNESS』(2021年/台湾)
感染ではなく“覚醒”──理性を失った人間の暴力が都市を支配する。
台湾発のスプラッターホラーとして世界中で話題となった本作は、感染した人々が暴力と性的衝動に支配されるという極めて過激な設定を持つ。ゾンビのような存在ではなく、知性を保ったまま残虐行為に走る人間たちの描写が恐ろしく、強姦、拷問、集団暴行といった描写が連続する。視覚効果は洗練されており、スピーディーな展開とスタイリッシュな映像美が、逆に暴力の異常性を際立たせている。世界各地で上映禁止やR指定を受けた背景には、その倫理を問う内容の過激さがある。パンデミック以降の社会を象徴する作品として、恐怖と不快感を極限まで突き詰めた現代ホラーの代表格と言えるだろう。
『テリファー』(2016年/アメリカ)
ピエロ恐怖症でなくとも、今夜は眠れなくなる。
殺人ピエロ「アート・ザ・クラウン」が繰り広げる拷問と殺戮を描いたスラッシャー作品。特に、人体を縦に真っ二つに切断するシーンは、視覚的インパクトがあまりに強烈で、多くの視聴者がトラウマ的な印象を抱いたとされる。スプラッター描写へのこだわりが強く、低予算ながらも確かな恐怖演出が話題を呼んだ。2024年にはシリーズ最新作『Terrifier 3』が全米公開され、今作ではクリスマスの街を舞台に、アート・ザ・クラウンがまたもや容赦ない殺戮を展開した。

『ソウ』(2004年/アメリカ)
“生き残る意思”が試される、血塗られた頭脳戦の幕開け。
ジェームズ・ワン監督の出世作となった『ソウ』は、猟奇的な連続殺人鬼「ジグソウ」が仕掛ける“ゲーム”に巻き込まれた人々の運命を描く。視聴者に印象づけられるのは、拷問器具のようなトラップの数々であり、犠牲者が生き残るために自らの身体を損なう決断を迫られるシーンだ。サイコスリラーとグロテスク描写が見事に融合した作品として、シリーズを通して過激さと哲学性のバランスを保ち続けている。
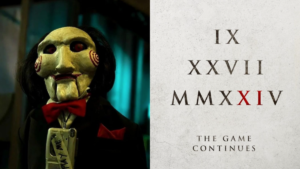
『悪魔のいけにえ』(1974年/アメリカ)
電動ノコギリが唸る、“最恐”食人一家の原点。
トビー・フーパー監督によるホラー映画の金字塔。レザーフェイスが電動ノコギリを振り回す姿は、ホラー史に残るアイコン的存在となった。直接的な流血描写は少ないが、不快な音響やカメラワークにより、想像力を刺激する残虐性が際立っている。食人や監禁といったテーマも、当時の倫理観を大きく揺るがすものだった。現代のホラーに多大な影響を与えた作品であり、その後のサブジャンル形成にも寄与している。
『ミッドサマー』(2019年/アメリカ)
美しさの裏に潜む“儀式”──陽光の下で行われる恐怖。
アリ・アスター監督による“昼のホラー”とも評される異色作。北欧の村で行われる夏至祭を舞台に、開放的な風景のなかで次第に狂気が広がっていく。高所からの飛び降りによる即死描写や、宗教儀式を装った生贄の場面など、ショック性のあるシーンが淡々と描かれるのが特徴だ。派手なスプラッターではなく、視覚的に美しい世界観の中で進行する暴力性が、観る者の不安を増幅させる。

こうした過激なホラー映画は、単なるショック演出としての「グロテスク」では終わらない。それぞれの作品には、人間性、暴力、支配、苦痛といった根源的なテーマが横たわっている。倫理の境界を問いかける表現が、逆に観る者の価値観や感性を試すことになる。安易な閲覧は勧められないが、映像表現の極北にある問いに向き合いたいと願う者にとっては、避けて通れない作品群と言えるだろう。